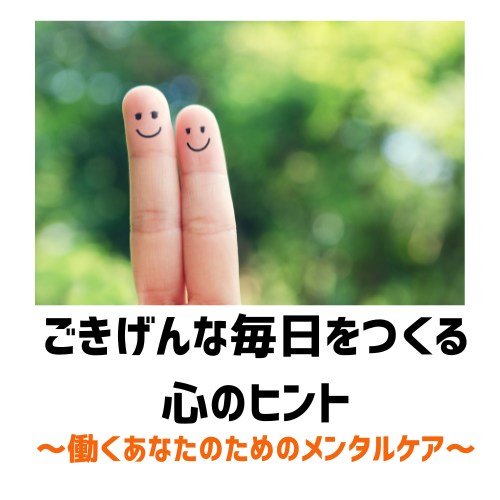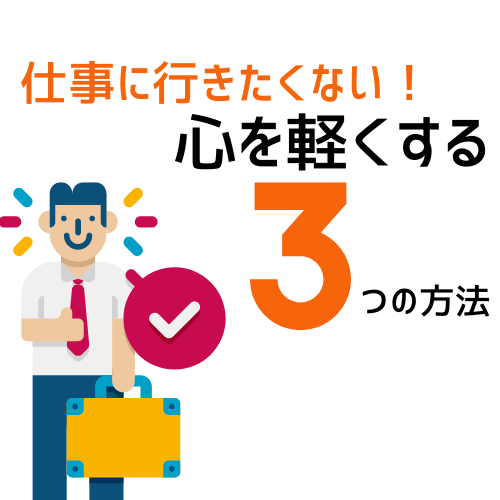~人事・健康経営担当者が今すぐ始めたい、心のケアと定着支援の実践ガイド~
離職率の上昇、採用難、定着率の低下……。昨今の企業経営において「人材」は最も重要な資源であると同時に、最も不安定なリスク要因でもあります。特に、表面上は順調に見える社員が、突然「辞めます」と言い出すケースに頭を抱えている人事担当者は少なくありません。
対策を講じてもすぐに成果が出るとは限らない――これは、メンタルヘルスや離職対策の難しさでもあります。「制度を整えても、人が辞めてしまう」「取り組みを理解してもらえない」という企業の声も多く寄せられます。
ですが、その取り組みは決して無駄ではありません。問題は“効果がない”のではなく、“伝わっていない”可能性があるのです。現場との対話や関係性をどう築くか。そこに、次の改善へつながる“気づき”があるかもしれません。
突然の離職の背景にあるもの、それはしばしば「メンタル不調」です。本記事では、離職の陰に隠れた“心のサイン”に企業がどう気づき、支援し、離職を防いでいくべきかについて、心理的観点から解説します。
1. なぜ「突然の退職」が起きるのか?
表面化しない“心の声”に耳を傾ける
ある日突然、期待していた若手社員が退職を申し出てきた——。そんな経験をされた企業も多いのではないでしょうか。実は「突然の退職」と感じるのは企業側だけであり、本人にとっては数ヶ月、あるいは数年の葛藤の末の結論であることがほとんどです。
退職の理由には、人間関係、評価制度、キャリアパス、業務負担など様々な要因がありますが、多くの場合に共通するのは「話せなかった」「助けを求められなかった」という心理的孤立です。
「誰にも相談できない」環境が心の負担を増幅させる
心理的に孤立している人は、悩みや不満を外に出すことができません。
例えば、上司に意見を言っても理解してもらえない、同僚と雑談すらできない。そんな状態が続くと、小さなストレスでも発散できずに積み重なっていきます。
最終的に、「自分の存在が軽んじられている」「ここに居場所はない」と感じるようになり、退職を“逃げ道”として選ぶようになるのです。
「わかってもらえない」と感じることで組織との信頼が崩れる
心理的孤立の背景には、「話してもどうせわかってもらえない」という諦めがあります。
その気持ちが強くなると、組織との信頼関係が崩れ、「この会社には自分の味方はいない」という思いに繋がっていきます。信頼が崩れた状態で働き続けることは、強いストレスです。次第に「辞めたほうがラクだ」と感じてしまうのです。
自己評価の低下が離職意欲を高める
孤立していると、自分の仕事が誰の役に立っているのかが見えづらくなります。
上司からのフィードバックが少なかったり、成果を認められる場がなければ、自己肯定感が下がります。「どうせ自分なんていなくても困らない」「このままいても評価されない」という思いが、“辞めたくなる理由”として心に根を張っていくのです。
孤立状態では職場に「安心感」を持てない
メンタルヘルスの観点では、「心理的安全性(言いたいことを言える、助けを求められる環境)」が保たれていることが非常に重要です。しかし、孤立した社員は、本音を話す相手も、失敗を許容してくれる空気もないと感じています。
その結果、「この環境にいるのは自分のためにならない」と判断して離職に至るのです。

2. メンタル不調がもたらす“見えない損失”
企業にとっての損失は離職だけではない
メンタル不調が原因で社員が退職する場合、企業は以下のような損失を被る可能性があります。
- 採用コスト(中途採用で1人あたり平均数十万円〜数百万円)
- 育成コスト(OJT・マニュアル整備・教育担当者の時間)
- 生産性の低下(業務の属人化による混乱や納期遅延)
- チームのモチベーション低下(他社員への心理的影響)
さらに長期的には、企業文化や職場環境への信頼性が損なわれ、エンゲージメントの低下、ブランドイメージへの悪影響など、“目に見えない損失”が広がっていきます。
3. 離職の前兆を示す「6つのメンタルサイン」
行動の変化に現れる初期症状
メンタル不調は、身体的な症状のように明確な変化が現れるとは限りません。ですが、注意深く観察すれば共通した「兆候」が存在します。
- 会話や発言が減る(以前より消極的・表情が乏しい)
- 遅刻や休暇の頻度が増える(月曜や連休明けに多い)
- 小さなミス・確認漏れが増える
- 報連相が雑・またはなくなる
- 自己否定的な発言が増える(「自分はダメだ」「役に立てていない」)
- 過剰に業務を抱え込む(周囲に頼れず無理をしてしまう)
これらのサインは、いずれも早期対応によって改善できる可能性がありますが、放置すると「退職」という結果でしか現れなくなります。
4. 組織でできる実践的なメンタルヘルス対策
(1)ストレスチェックの“活かし方”を見直す
ストレスチェック制度は、2015年の法改正により従業員50人以上の事業所に年1回の実施が義務付けられました。多くの企業が形式的に実施していますが、本来の目的は「職場のストレス要因を把握し、改善につなげること」です。つまり、“実施すること”がゴールではなく、“結果をどう活用するか”が本質なのです。
① 高ストレス者への適切なフォロー
ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された従業員には、医師による面接指導を実施することができます。しかし、面談を希望するハードルが高いため、本人から申し出がないまま放置されるケースも少なくありません。
企業としては、面接指導の案内をわかりやすく丁寧に伝え、心理的安全性のある形で利用を促すことが大切です。人事や上司からのフォローの声かけや、社外相談機関の紹介なども効果的です。
② 組織ごとのストレス状況を“見える化”する
ストレスチェックでは、個人結果だけでなく、部署ごとの集団分析が可能です。「どの部署がストレス要因を多く抱えているのか」「何が主なストレッサーなのか(上司・同僚・業務量など)」を把握することで、組織的な課題が明確になります。
例えば、「評価への不満が多い部署」「上司との関係性に課題がある部署」「仕事の裁量が少ないと感じている部署」など、数値とデータに基づいて職場改善を検討できるようになります。
③ 職場改善への具体的アクションへつなげる
集団分析結果を受けて、以下のようなアクションを検討しましょう:
- 業務量の偏り是正(業務配分や人員配置の見直し)
- コミュニケーション活性化(朝礼・定例会・1on1の強化)
- 評価制度の透明化(公平感・納得感のある基準づくり)
- 上司研修の実施(マネジメント力・傾聴力の強化)
重要なのは、「数値が悪い=叱責や責任追及」ではなく、「職場をより良くするチャンス」と捉える前向きな姿勢を持つことです。
④ 継続的なモニタリングと対話
ストレスチェックは年1回の実施で終わらせず、半年ごと、四半期ごとに簡易調査や社員アンケートを実施することで、組織の“温度感”を継続的に把握することができます。
また、結果は経営陣だけでなく、現場マネージャーにも共有し、現場レベルでのフィードバック・対話を通じて改善の意識を広げていくことが理想です。
(2)1on1ミーティングを仕組み化する
面談の「実施頻度」「面談者のトレーニング」「信頼関係の構築」が重要です。社員が“安心して話せる場”を持てることで、離職の未然防止につながります。
(3)社内相談窓口・外部支援機関との連携
社内に産業保健師や従業員支援プログラム等の窓口があれば、早期にプロが介入し対応できます。中小企業では、外部のメンタルヘルス支援サービスを利用するのも現実的です。
(4)人事・上司の“感度”を高める研修
管理職向けのメンタルヘルス研修は非常に効果的です。「気づき力」「声かけ力」を身につけることで、職場の安全網を強化できます。
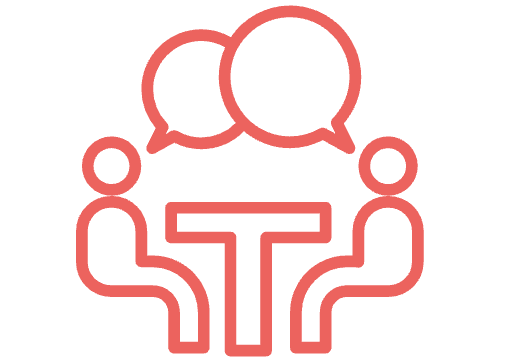
5. 健康経営とメンタルケアの関係性
経済産業省が推進する「健康経営」では、身体面だけでなく心の健康管理も重要視されています。実際、健康経営優良法人認定の評価項目にも、「ストレスチェックの活用」「メンタルヘルス教育」「相談体制の整備」などが含まれています。
メンタルケア=コストと捉えがちですが、実際には従業員の生産性向上、離職防止、企業ブランド向上といった明確なメリットが得られます。
6. これからの時代に必要な“心理的安全性”
Googleが実施した「効果的なチーム」に関する研究(プロジェクト・アリストテレス)でも、最も重要な要素として挙げられたのが「心理的安全性」です。
心理的安全性とは、自分の考えや感情を自由に表現できる安心感のこと。メンタル不調や不満を抱えている社員が「話してもいい」と感じる職場環境こそ、強いチームの土台となります。
7. まとめ:心の声に耳を傾ける組織が、人を守り、人を活かす
離職には必ず理由があります。そして多くの場合、その理由は“心”にあります。
人事や健康経営の担当者は、単に制度を整えるだけでなく、人の変化に気づき、寄り添い、信頼関係を築く存在としての役割が求められています。
「最近元気がないな」
「話す機会が減っているな」
そんな小さな気づきが、社員の未来を、企業の未来を守ります。
今こそ、メンタルヘルス対策を「経営の一部」として捉え、離職を防ぐだけでなく、働く人が安心して力を発揮できる職場づくりを一緒に目指していきましょう。
併せて読みたい▼
メディワークでは、ヘルスケアの専門的な知識を持ったプロフェッショナルが企業や組織のチームの成功をサポートしています。無料ヒアリングも承っております。職場の健康づくりにお悩みでしたらお気軽にお問い合わせください(^ ^)
お問い合わせは専用フォームから24時間いつでも受け付けております。